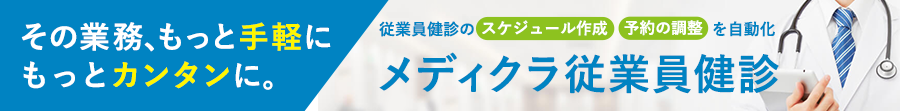ストレスチェックとは?
「ストレスチェック」とは、働く人のストレス状態について調べる簡単な調査です。ストレスに関する質問表に働く人が回答をし、それを集計・分析することで、職場のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを調べます。
「労働安全衛生法」が改正された、2015年12月から、毎年1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられました。
令和4年の調査によると、
メンタルヘルスの不調により連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.6%です。
また、現在の仕事や職業生活に関することで不安やストレスを感じている従業員の労働者の割合は約8割に上ります。
ストレスによる休職者が、職場内で出ることはとても身近なことなのです。
従業員の心の健康に常日頃から気を配り、安心して働くことのできる職場環境を整えておくことで、うつ病などのメンタルヘルスの不調により休職者が出ることを未然に防ぐことが出来ます。
とはいえ、心の状態は目に見えるものではなく、なかなか把握がしづらいという現状があります。
そんなとき、ストレスチェックが従業員の心の状態を知るきっかけとなるでしょう。
ストレスチェックの効果は?
ストレスチェックは、具体的にどのような効果があるのでしょうか?
ストレスチェックは労働者が自身の職場でのストレス状況を把握することを目的に開発されました。
厚生労働省が行ったアンケート調査によると、ストレスチェック制度を行ったことにより、53.1%の事業者が「社員のセルフケアへの関心の高まり」を実感したと回答をしました。また、「メンタルヘルスに理解ある風土の醸成」や「職場の雰囲気の改善」もストレスチェック制度の効果として挙げられています。(厚生労働省:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて,p4)
労働者自身もストレスチェック制度の効果を実感し、メンタルヘルスの改善に役立ったという声が多くあります。
アンケート調査では「自身のストレスを意識するようになった」と、労働者の約半数以上が回答しています。
ストレスチェックを継続的に行った事業所の中には、実施前と比べて、メンタルヘルス不調者が5分の1に減少したところもあるそうです。
ストレスチェック実施を効果的に行うことで、健康かつ健全な職場の雰囲気作りや、社員のストレス減少に役立てることが出来るのです。
ストレスチェックの効果的な活用の仕方
効果的なストレスチェックを実施するにはどうしたら良いでしょうか?
ストレスチェックはただ実施するだけではなく、その結果をうまく活用することで労働者のストレス改善に大きな効果を得ることが出来ます。ここではストレスチェックを効果的に活用するポイントを紹介します。
① 集団分析を行う
ストレスチェックの実施後に、結果をよく分析して、職場の改善点を考えることが活用のポイントとなります。
その結果の分析には「集団分析」を行うことで、職場の状況や課題を可視化することが重要です。
「集団分析」とは「ストレスチェックの結果を部署ごとに集計をして、その結果を集団という単位で解釈すること」をいいます。
集団分析は努力義務ですが、結果を職場環境改善に生かす際に大いに役立ちます。
部署などの単位で結果を集計すると以下のようなことが分かってきます。
・仕事のコントロール度が高い部署はどこか
・仕事の量的負担が高く過重になっている部署はどこか
・上司や同僚の支援が標準集団(全国平均)と比べてどの程度なのか
・予測される疾病休業などの健康問題のリスクの評価
これらの分析を踏まえて、どのようにしたら健康な職場づくりが出来るのかを考えていきましょう。
人数が少ない場合に集団分析を行う際は、プライバシーを守ることに特に気をつけなければなりません。
分析する部署単位の人数が少なくなると、特定の人の回答が分析結果に影響を与えてしまいます。
その結果として回答者のプライバシーが守られないことにもつながる恐れがあります。
ストレスチェックの受検は労働者にとって義務ではありませんが、受検にあたりストレスチェック制度の意義を労働者に説明し、理解を得ることで高い受検率を確保できるようにしましょう。
また、どうしても分析人数が小さくなってしまう場合、分析結果が一部の管理監督者のみに返却するよう対象を検討することも考えましょう。
② 結果に基づいた職場環境の改善を行う
集団分析結果をもとに、職場環境の改善を行うことで、ストレスチェックの実施を効果的にすることが出来ます。
結果をヒントに現実的にはどのような問題があるのか、具体的にどのように職場環境を改善できるかを検討しましょう。
さらに職場改善の計画を立て、実行に移しましょう。
職場環境の改善点を見つけるときは、問題点の指摘ではなく「どうするとより良くなるか」を検討することがポイントとなります。
労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェック実施が義務
前述の通り、2015年よりストレスチェックの実施が義務付けられましたが、すべての事業所に対し実施義務があるわけではありません。
労働安全衛生法施行令の第五条には「法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。」とあり、
労働者が50人を超える場合に実施義務があるとされています。
ただし、現在の従業員数が50人未満でも、今後の法改正でストレスチェックの実施が義務付けられるかもしれませんので、ストレスチェック制度について、あらかじめ把握しておくことも大切です。
労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェック結果報告が義務
ストレスチェックは、実施のみでなく結果の報告にも義務があることにも留意しておきましょう。
労働安全衛生規則の第五十二条の二十一に「常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の 二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」とあり、
実施義務のある事業所は、通常の健康診断と同様、ストレスチェックの結果を労働基準監督署に提出しなければなりません。
報告書の作成の際は、厚生労働省が公開している、以下の様式に従って作成する必要があります。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
50人未満の事業所でも実施したほうが良い理由は?
ここまで、従業員が50名以上の事業所を対象にストレスチェックの内容、実施項目について説明してきましたが、2024年1月時点では、従業員が50人未満の事業所では、ストレスチェックは努力義務とされています。
しかしながら、従業員が50人未満の場合でも、従業員の心の状態を常に知っておくためにも、ストレスチェックの実施が有効です。
ストレスチェックの実施にあたっては、国は都道府県ごとに産業保健総合支援センターを設置して、小規模の事業場に対して産業保健のサービスを無料で提供しています。
産業保健総合支援センターの訪問支援を受けたり、ストレスチェック結果を踏まえた面談支援を地域産業保健センターに依頼することができます。
小規模事業場が健康管理システムを利用してストレスチェックを実施する場合は初期費用の補助があります。
「エイジフレンドリー補助金」
小規模事業場が健康診断結果などを保存、管理のためのシステム導入の初期費用の3/4上限30万円の費用補助があります。
産業保健総合支援センターの支援に関しては以下のサイトをご覧ください。
● 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)について
産業保健総合支援センター(さんぽセンター)| 労働者健康安全機構
労働健康安全機構の助成金については以下のサイトで詳細をご確認ください。
● 労働健康安全機構の助成金について
助成金 | 労働者健康安全機構
近年メンタル不調による休職者が増えています。
健康経営を推進するうえでもストレスチェックを実施し、メンタルヘルス対策をしていくことが重要になります。
ストレスチェックの実施には少なからず費用がかかりますが、これらの支援制度を利用することができれば、ストレスチェック実施のハードルが少し下がるのではないでしょうか。
[参考文献]
ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル : 厚生労働省【PDF】
ストレスチェック制度の実施状況(令和4年) : 厚生労働省【PDF】
ストレスチェック制度について : こころの耳
厚生労働省 労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル : 厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室【PDF】
ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて : 厚生労働省【PDF】
仕事のストレスを改善する職場環境改善のすすめ方 : 厚生労働省【PDF】